
徳川家の身内筋である御三卿の一つが一橋家です。その一橋家の当主、一橋治済(はるさだ)は当時、重要人物と考えられていました。
2025年のNHK大河ドラマ「べらぼう」では、この一橋治済役のキャストとして生田斗真が出ています。
 |
ここでは一橋治済について見ていきます。
一橋治済とは
一橋家とは
一橋治済(はるさだ)は一橋家の初代当主、一橋宗尹(ひとつばし むねただ)の四男として生まれました。父の一橋宗尹は8代将軍、徳川吉宗の四男です。従って、治済は吉宗の孫ということになります。
 |
一橋家は田安家、清水家と共に御三卿と言われ、紀州、尾張、水戸の御三家とともに徳川姓を称することが許されていました。ですから、一橋治済は徳川治済とも言います。
御三卿は江戸時代中期に作られました。8代将軍、徳川吉宗と9代将軍、徳川家重の子がそれぞれ初代当主となっています。家格としては御三家に準ずる高い家格の家柄でした。
御三卿は最終的に10万石の賄料をもらうようになりましたが、尾張、紀州、水戸などの御三家とは違い、所領を持つ大名ではなく、あくまで将軍家の部屋住みといった待遇でした。
ですから他家に後継ぎが無い場合、養子を出す役割を果たしており、将軍家に後継ぎがいない場合には、その後継ぎとなる資格を有していました。
一橋治済の略歴
一橋治済は宝暦元年(1751年)に一橋宗尹の四男として生まれたと述べました。母は細田時義の娘、由加で宗尹の側室です。幼名を豊之助と言いました。
治済の兄を見ると、長男の重昌は越前福井藩に養子に行き、福井藩主となっています。次男、仙之助は夭逝しています。三男の重富は兄、重昌の死去に伴い、越前福井藩主を継いでいます。また、弟の五男、治之は福岡藩の黒田家当主となっています。
一橋家は四男の治済が継ぎ、明和元年(1764年)に2代目の当主となりました。
田沼家との関係
田沼意次の弟、田沼意誠(たぬま おきのぶ)は後に一橋家の初代当主となる徳川宗尹の小姓となりました。その後、一橋家の家老にまで昇進し、最終的には800石取りとなりました。
御三卿の家臣の多くは幕府からの出向扱いだったので、意誠も幕府の旗本でした。一橋家の家老職は子の田沼意致(おきむね)に引き継がれます。
このように田沼家との縁にもかかわらず、一橋治済は反田沼の急先鋒である松平定信を支持する反田沼派の黒幕とされています。
徳川家基の死
10代将軍、徳川家治には世子である徳川家基がいました。名前に”家”という字がつけられていることで、11代将軍となることが規定路線になっていたことがわかります。
しかし、家基は18歳の若さで世を去ります。鷹狩りに行った際、体調不良を訴えて、そのまま亡くなったのです。
こうした経緯から毒殺が疑われたのもやむをえません。犯人として田沼意次や一橋治済の名がささやかれています。
家基は田沼に批判的であったとされ、家基が将軍になると自らが失脚することを恐れて、田沼が暗殺したという説や、跡取りの家基がなくなれば、一橋家に将軍職が回ってくることを見越して一橋治済が行ったという説などがあります。
いずれにしても、真相は藪の中です。
11代将軍徳川家斉の就任
跡取りがいなくなった10代将軍家治の後、それを継いだのが一橋治済の子である11代将軍、徳川家斉です。

このタイミングで、田沼意次は失脚させられ、田沼派が完全に凋落します。それに代わって、松平定信が老中筆頭となり、寛政の改革が実施されます。
こうした政変の背後に一橋治済がいたとされています。
松平定信の失脚

寛政の改革と言われる様々な改革を実施した松平定信は一定の成果を上げました。しかし、その反動で批判的な意見も多かったようです。そうした中、老中を辞任し、失脚することになります。
その原因は尊号一件とされています。これは朝廷と幕府の間で起こった問題です。以下、尊号一件について見ていきます。
閑院宮典仁親王の太上天皇問題
朝廷では後桃園天皇が崩御した後、後継者として師仁親王が即位して光格天皇となりました。しかし、光格天皇の父、閑院宮典仁親王は摂関家よりも下とされていました。そこで、光格天皇は父を敬うため、天皇になっていない父に「太上天皇」、いわゆる上皇の尊号を贈ろうしました。
これに対して、松平定信は過去に例がないと反対しました。実は過去に天皇にならずに太上天皇の称号を贈られた例はありましたが、それは動乱の時期の例外としました。
一橋治済の大御所問題
実はこれと全く同じ状況が幕府の側でも生じました。それは11代将軍、家斉が自分の実父である一橋治済に「大御所」の称号を贈ろうとしたからです。大御所というのは将軍職を退いた前将軍に対する尊称でした。
将軍になっていない一橋治済に対して、こうした称号を贈ることに対して、松平定信は先例が無いと反対しました。これは朝廷の太上天皇号を拒否した手前、そうせざるを得なかったという点と、一橋治済のさらなる権力強化に対する脅威があったのでしょう。
しかし、これは将軍と実父、一橋治済の怒りを買い、定信の失脚につながったとされています。
隠然たる権勢
11代将軍、家斉は子沢山で知られています。何と53人の子どもが生まれ、その内28人が成人しました。子供は御三家、御三卿をはじめ、各大名家に養子、あるいは嫁いでいます。
こうした養子や婚姻戦略は自らの基盤を確立するために利用されたと思わます。気づけば将軍、家斉の誕生をはじめ、一橋家の興隆がもたらされていることがわかります。
これらの背後で一橋治済は隠然たる権勢を誇っていました。様々な事件の黒幕と考えられているのもあながち虚構とは言えないことがわかります。

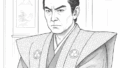

コメント