
NHK大河ドラマ「べらぼう」に登場する人物の辞世の句を集めてみました。
最後に詠んだ句はその人の人生を表すと言われています。
それでは見ていきましょう!
太田南畝の辞世の句
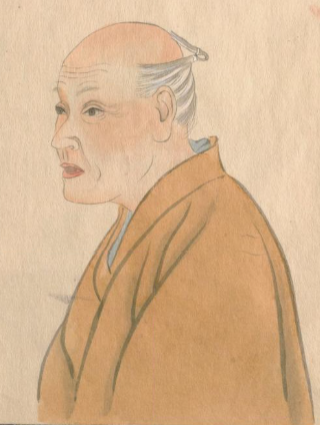
大田南畝(おおた なんぽ)
【寛延2年(1749年)- 文政6年4月6日(1823年)】
昨日まで 人のことかと 思いしが 俺が死ぬのか それはたまらん
朱楽菅江の辞世の句
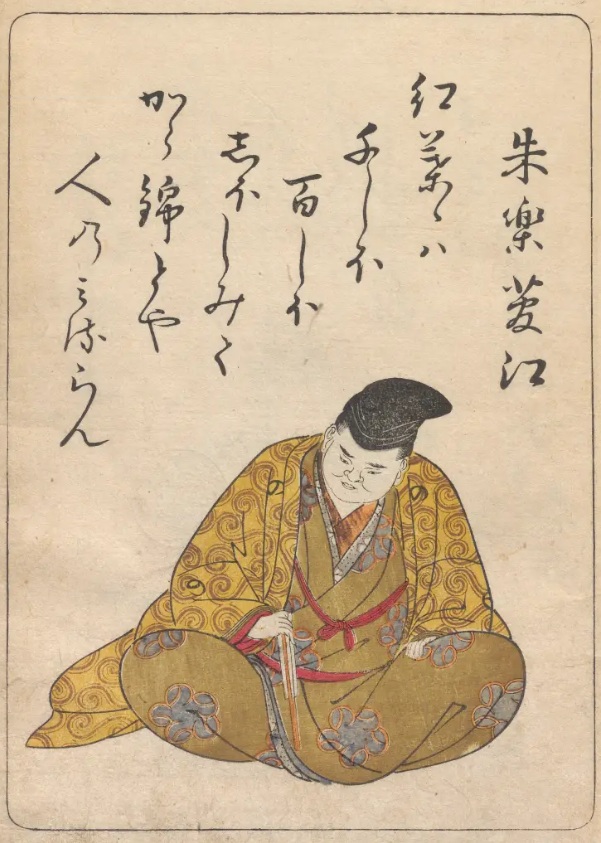
朱楽菅江(あけら かんこう)
【元文5年(1740年) – 寛政10年12月12日(1799年)】
執着の 心や娑婆に 残るらん 吉野の桜 さらしなの月
意味:もうすぐ死ぬ私ですが、この世に執着する心が残っています。吉野の桜や更科の月が見れなくなるのは残念だなぁ。
元木網の辞世の句
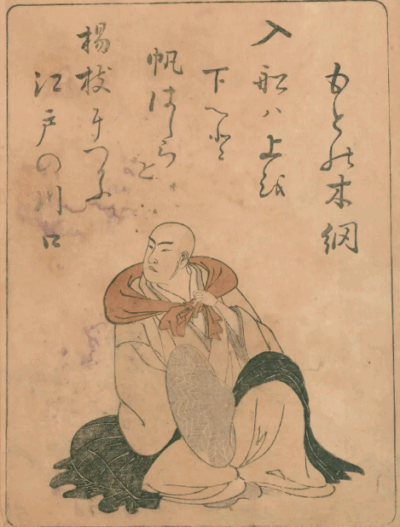
元木網(もとの もくあみ)
【享保9年(1724年) – 文化8年6月28日(1811年)】
あな涼し 浮世のあかを ぬぎすてて 西へ行く身は 元のもくあみ
智恵内子の辞世の句
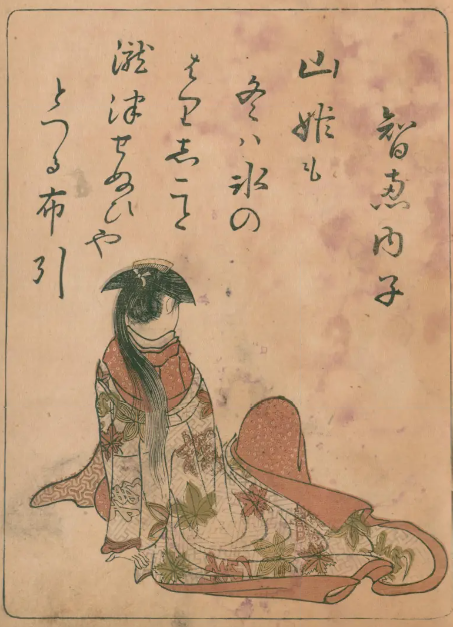
智恵内子(ちえの ないし)
【延享2年(1745年) – 文化4年6月20日(1807年)】
六十あまり 見はてぬ夢の 覚むるかと おもふもうつつ あかつきの空
平秩東作の辞世の句
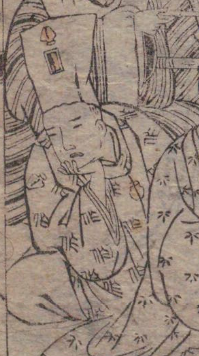
平秩東作(へづつ とうさく)
【享保11年(1726年) – 寛政元年3月8日(1789年)】
南無阿弥陀 ぶつと出でたる 法名は これや最後の 屁づつ東作
平賀源内の辞世の句

平賀源内(ひらが げんない)
【享保13年(1728年) – 安永8年12月18日(1780年)】
乾坤(あめつち)の 手をちぢめたる 氷かな
朋誠堂喜三二(手柄岡持)の辞世の句
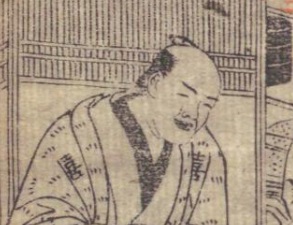
朋誠堂喜三二(ほうせいどう きさんじ)
【享保20年(1735年)- 文化10年5月20日(1813年)】
狂歌よむ うちは手柄の 岡持も よまぬだんでは 日がらの牡丹餅
恋川春町(酒上不埒)の辞世の句
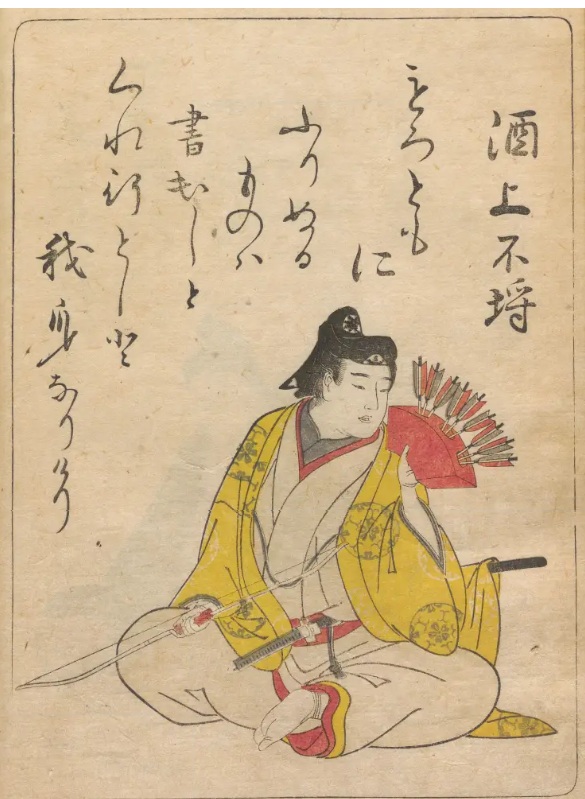
恋川春町(こいかわ はるまち)
【延享元年(1744年)- 寛政元年7月7日(1789年)】
我もまた 身はなきものと おもひしが 今はのきはぞ くるしかりけり
北尾政演(山東京伝)の辞世の句

北尾政演(きたお まさのぶ)
【宝暦11年(1761年) – 文化13年9月7日(1816年)】
耳をそこね 足もくぢけて 諸共に 世に古机 汝も老いたり
唐来三和の辞世の句

唐来三和 (とうらい さんな)
【延享元年(1744年)- 文化7年1月25日(1810年)】
かりの世の 地水火風を もどすなり これで五輪の さしひきはなし
松平定信の辞世の句

松平定信(まつだいら さだのぶ)
【宝暦8年(1759年) – 文政12年5月13日(1829年)】
今更に 何かうらみむ うき事も 楽しき事も 見はてつる身は
意味:今さら何を恨もうというのか。辛い事も、楽しい事も見果てた身では…
佐野政言の辞世の句

佐野政言(さの まさこと)
【宝暦7年(1757年) – 天明4年4月3日(1784年)】
こと人に 阿らて御国の 友とち たたかひすつる 身はゐさきよし
卯の花の 盛りもまたで 死手の旅 道しるべを 山時鳥
卯の花の 盛を捨て 死出の旅 山時鳥 道しるべせよ
勝川春章の辞世の句
勝川春章(かつかわ しゅんしょう)
【享保11年(1726年)/寛保3年(1743年) – 寛政4年12月4日/8日(1793年)】
枯ゆくや 今ぞいふこと よしあしも
鳥山石燕の辞世の句
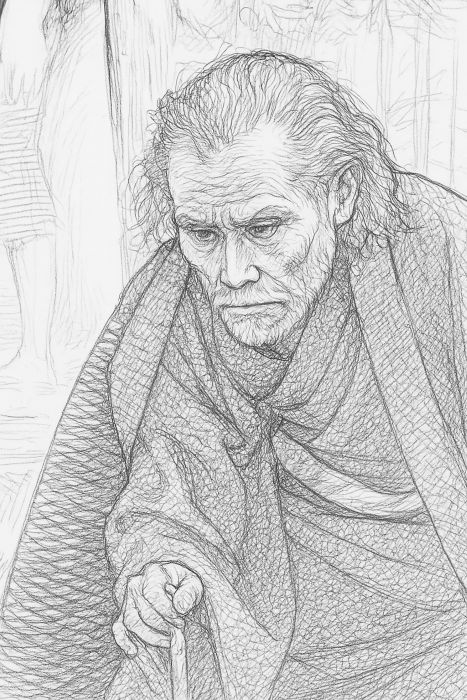
鳥山石燕(とりやま せきえん)
【正徳2年(1712年) – 天明8年8月23日(1788年)】
隈刷毛の 消ぎはを見よ 秋の月
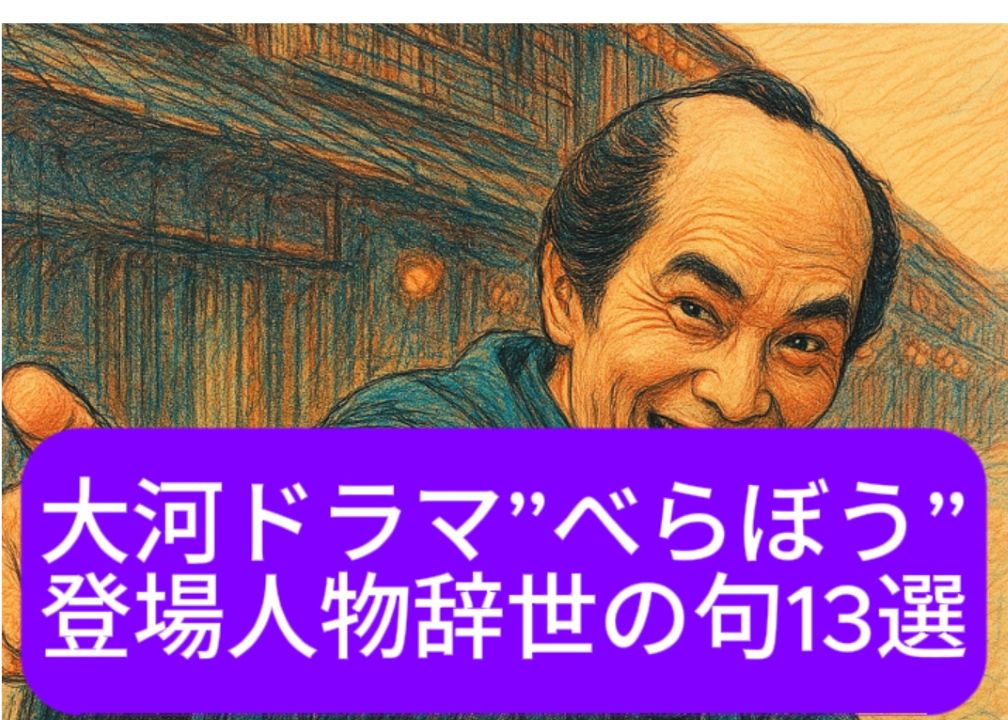
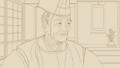

コメント