
寛政の改革を主導した老中、松平定信。歴史の教科書などでもお馴染みの人物です。
2025年のNHK大河ドラマ「べらぼう」ではその若いころの田安賢丸(たやす まさまる)役のキャストとして寺田心が出演しています。
 |
また、成長した松平定信役のキャストを井上祐貴が演じています。
 |
ここでは松平定信が老中に就任するまでについて述べていきます。
松平定信とは
松平定信の略歴
御三卿の田安家に生まれる
定信は宝暦八年(1759年)に御三卿の一つ、田安徳川家の初代、徳川宗武の七男として生まれました。母は側室の香詮院(山村とや)です。
まずはこの御三卿について見ていきます。
この御三卿というのは八代将軍吉宗以降の時代に成立した徳川将軍の一門で、田安家、一橋家、清水家の三家からなります。
田安家初代の徳川宗武は8代将軍吉宗の三男、一橋家の徳川宗伊は吉宗の四男、清水家の徳川重好は9代将軍家重の次男でした。
徳川家康の子を始祖とする紀州、尾張、水戸の御三家と同様、御三卿は徳川姓を使用することが認められていました。御三家に匹敵するぐらいの家格でしたが、独自の藩を持たず、将軍の親族として10万石の賄料を貰う形式、いわば”将軍家の部屋住み”でした。
この特異な存在形態である御三卿は将軍家に後継ぎが無い場合、そこに迎えられる可能性があるとともに、御三家や他の大名家などに後継ぎが無い場合、養子となる身分の高い部屋住みだったと言えます。
白河藩への養子問題
田安家では宗武の子は長男から四男までが早逝しました。そのため、明和八年(1771年)に宗武が死去した後、正室、宝蓮院の子で五男の徳川治察(はるあき/はるさと)が跡を継ぎました。
田安宗武には、この治察以外に側室の生んだ六男の定国と七男の定信がいました。六男の松平定国は定信の同母兄で、伊予松山藩主、松平定静の養嗣子となっていました。
一方、七男の松平定信は安永三年(1774年)三月に陸奥白河藩主、松平定邦の養子となることが決まりました。ですが、しばらく田安屋敷で暮らしていました。
まだ若い田安治察に後継ぎがおらず、田安家の後継者となりうる定信を白河藩に養子に出すことに治察は反対していましたが、将軍家治の命で決まったようです。
その背景には家格上昇を狙う白河藩の意向と田沼意次の意向があったようです。背後に一橋家の動きがあったかは定かではありません。
田安賢丸(たやす まさまる)への期待
少し、時代をさかのぼり、松平定信の幼少期、すなわち田安賢丸時代を見てみましょう。当時、田安家では五男の治察が病弱で凡庸だったこともあり、聡明だった賢丸に田安家の後継候補として期待が集まっていました。
また、将軍家治の後継という期待もあったようですが、家治の実子、家基が生まれ、文武両道に優れていたことで、家基が正当な後継者となりました。
こうして将軍後継への道は将軍の実子、家基がいるので潰えていましたが、田安家を継承する道は残っていました。
田安家の継承と養子の解除
ところが白河藩の養子となることが決まった安永三年(1774年)三月から約半年後の九月、なんと田安治察が20代前半で亡くなります。田安家を継いでわずか3年後のことです。このとき、治察には妻子はいませんでした。
定信は既に白河藩主の養子となっていましたが、いまだ田安屋敷に暮らしていました。こうしたことから、白河藩との養子縁組を解消し、田安家を継承することを希望します。
しかし、これは認められず、田安家は以後、当主不在の状態となります。松平定信はそもそも白河藩へ養子に行くことを望んでおらず、この件について、田沼をはじめとする老中連中を恨んでいたようです。
天明の大飢饉と白河藩
天明二年(1782年)からはじまった気候不順による影響は、天明三年(1783年)には岩木山、それに続いて浅間山の噴火による火山灰の影響で、農業に深刻な影響をもたらしました。
これがいわゆる天明の大飢饉で、餓死者が続出するなど、江戸期の飢饉の中で最も被害が大きかったと言われます。これには米価高騰による江戸への廻米など政策的な失敗も大きく人災的な側面もありました。
これにより東北地方を中心に数十万人の人が亡くなりました。関連死を含めれば100万を超えるとも言われています。こうした中、同じ東北でも米沢藩や白河藩では様々な対策により餓死者が出なかったと言われています。
松平定信の老中就任
こうした治世の実績をたずさえて、天明七年(1787年)に白河藩の松平定信が老中に登用されます。しかもいきなり老中の中でもトップである老中首座になります。
これには御三家、つまり尾張の徳川宗睦(むねちか)、紀伊の徳川治貞(はるさだ)、水戸の徳川治保(はるもり)や御三卿の一橋治済の支援があったようです。
田沼意次は前年に失脚しており、将軍も10代家治から11代家斉の時代になっていました。こうした反田沼派として松平定信が知られていますが、背後には一橋治済(はるさだ)の動きも指摘されています。
こうして老中に就任した定信は幕府を立て直すべく、以後、寛政の改革を推進していきます。

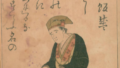

コメント