
「蔦屋重三郎の妻」の項で述べたように、妻については、その素性はおろか名前さえわかっていません。しかし、蔦重の母については、その名前が分かっています。また、生き別れていた実母と暮らすようになるというのも史実です。
2025年のNHK大河ドラマ「べらぼう」では、母のつよ役のキャストとして高岡早紀が出演しています。
 |
ここでは、蔦屋重三郎の母、つよについて述べていきます。
蔦屋重三郎の母 つよ とは
上記で述べたように、蔦屋重三郎については妻の情報がほとんどないのに、なぜ、母親について情報があるかといえば、ある資料が残っているからです。
それは太田南畝による蔦重の実母顕彰の碑文と石川雅望(宿屋飯盛)による喜多川柯理墓碣銘とです。南畝と宿屋飯盛は共に蔦屋重三郎と深く交流があった人物です。
南畝による実母顕彰碑文
まず、南畝による蔦重の実母顕彰碑文ですが、これは寛政四年(1792年)に母、津与(つよ)が病死した後、重三郎が南畝に頼んで母親の遺徳を讃えるために作ったものです。
元々、養家である蔦屋家歴代の墓碑の左側面に、この母の顕彰碑文が記載されていたようです。
母親の顕彰碑文は作られていますが、父親のものは作られていません。ここから母親に対する思いが強かったことがわかります。
顕彰文の全文を以下に記載します。
広瀬氏者書肆耕書堂母也。諱津与江戸人 帰尾陽人幼丸山氏 生柯理而出 柯理幼冒喜多川氏称蔦屋重三郎 其居近倡門 天明三年癸卯九月移居城東通油町而開一書肆 競刻快書大行 都下之好稗史者皆称耕書堂 寛政四年壬子十月廿六日広瀬氏病死葬城北山谷正法寺 癸丑二月柯理來請日小人七歳離母而複合有今日 願得片言志於墓以報劬労 予日吾見人破産而入曲中者矣未聞出曲中而起業者也 子之志不渝則蓋足以観母氏之遺教矣 銘日小説九百母徳可摘 寛政癸丑莫春南畝子題
これによると、蔦重の母は広瀬氏であり、江戸の人で名前は津与ということがわかります。尾張出身の丸山氏に嫁いで柯理(からまる)、つまり蔦重を生んだとあります。
蔦重は幼い時、母と別れて喜多川氏の養子となりました。
母の津与は寛政四年に病死し、城北の山谷正法寺に葬られました。
母の死後、蔦重は南畝に七歳で母と別れ、再び会うことができ、今日の自分がある。母の苦労に報いるために片言の言葉を捧げたいと述べ、この碑文ができました。
七歳で別れた母ですが、感謝の意を持っていたことが分かります。
喜多川柯理墓碣銘
一方、喜多川柯理墓碣銘にも母親の情報があります。これは、蔦屋重三郎が亡くなった後に建てられたもので、元々、養家である蔦屋家歴代の墓碑と並んで建てられていた蔦屋重三郎の墓碑に記載されていたものです。
ここには上記の実母顕彰碑文以外の情報も記載されています
それによると、津与の夫、つまり蔦重の父の名は重助で蔦重が吉原で生まれたことが分かります。
蔦重は吉原大門の近くで耕書堂を開きますが、その後、日本橋の通油町に移転します。その移転後、父母を迎えて、厚く養ったことが分かります。
全文は以下の通りです。
喜多川柯理本姓丸山称蔦屋重三郎
父重助母広瀬氏
寛延三年庚午正月初七日
生柯理於江戸吉原里
幼為喜多川氏所養
為人志気英邁
不修細節
接人以信
嘗於倡門外開一書舗
後移居油街
乃迎父母奉養焉
父母相継而没
柯理恢廓産業
一倣陶朱之殖
其巧思妙算
非他人所能及也
遂為一大賈
丙辰秋得重痼弥月危篤
寛政丁巳夏五月初六日謂人曰
吾亡期在午時
因処置家事決別妻女
而至午時笑又曰
場上未撃柝何其晩也
言畢不再言
至夕而死
歳四十八
葬山谷正法精舎
予居相隔十里
聞此訃音心怵神驚
豈不悲痛哉
吁予霄壌間一罪人
餘命唯怗知己之恩遇而巳
今既如此
嗚呼命哉
銘曰 石川雅望
人間常業 大田南畝
載在稗史
通邑大都
孰不知子
おわりに
以上述べてきたように。二つの資料があるため、蔦屋重三郎の母の様子も若干わかります。蔦重は幼くして喜多川家の養子となりますが、母親との絆はしっかりとあったことがわかります。
ですから、耕書堂の成功後に父母を迎えるとともに、母の死後には顕彰のための碑文を刻んだのでしょう。


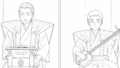
コメント